Home > 医学生・研修医向け情報 > 初期研修案内 > 研修プログラム > 2012年度 臨床研修プログラム > 選択必修科研修(4.精神科研修)

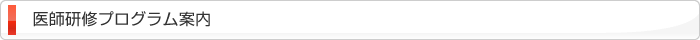
2012年度 臨床研修プログラム
2011.4.28 京都民医連中央病院臨床研修部
Ⅱ. 選択必修科研修 4. 精神科研修
研修期間は1.5ヶ月とする。
1. 緒言
医師の初期研修に際して、人間を単に生物的要素の集合体としてではなく全人的にとらえる視点は、極めて重要な獲得課題である。
しかし、身体医学を主とした初期研修期間においては、膨大な現代医学の知識および技能の獲得に追われてしまい、患者を、身体的だけではなく心理・社会的に(すなわち全人的または包括的に)理解することに困難が生じる可能性がある。
そこで、精神科研修では、身体医学領域の研修中に不足しがちな、全人的人間理解とそれに基づく臨床能力を獲得することを目的にして、以下の研修プログラムを用意した。研修医の積極的参加を期待する。
2. 研修目標
【行動目標】
- 基本的面接法を学ぶ。
- 精神症状の捉え方の基本を身につける。
- 精神疾患に関する基本的知識を身につける。
- 精神症状に対する初期的対応と治療の実際を学ぶ。
- 向精神薬の使い方に慣れる。
- 簡単な精神療法の技法を学ぶ。
- 心身相関についての理解を深める。
- 精神保健について基本的知識を身につける。
- 精神保健福祉法について理解を深める。
【経験目標】
(1)精神科関連で経験すべき診察法・検査・手技
- 精神医学的診察および精神症状の記載
- 神経生理学的検査(脳波など)について適応の判断、結果の解釈
- 臨床心理検査について適応の判断、結果の解釈
- 向精神薬による薬物療法
(2)精神科関連で経験すべき症状・病態[下線はレポート提出が必要]:
| 全身倦怠感 | 不安・抑うつ |
| 不眠 | |
| 体重減少 | 急性中毒 |
| 食欲不振 | 意識障害 |
| けいれん発作 | 精神科領域の救急 |
(3)精神科領域で経験すべき疾患:
1)入院患者を受け持ち、診断、検査、治療方針についてレポートを提出する疾患;
a.痴呆
b.うつ病
c.統合失調症
2)外来診療または受け持ち入院患者(合併症含む)で自ら経験する疾患;
d.身体表現性障害
3)その他;
e.症状精神病
f.アルコール依存症
g.不安障害(パニック障害)
3. 研修計画
(1)研修の基本構成パターン
全研修期間を奈良・吉田病院で実施する。
(2)研修内容
- 外来及び病棟での診察を陪席して、精神疾患の理解と、治療の実際について理解を深める。
- 外来新患の予診をとる。
- リエゾン・コンサルテーション症例を担当して、指導医との緊密な連携のもとで、診療にあたる(痴呆、うつ病の他,せん妄,身体表現性障害などを中心に)。受け持ち症例について、ケースレポートを作製する(臨床経過、考察を記載する)。
- 病棟および外来カンファレンスへ参加する。
- 副主治医あるいは看護者として入院症例(とりわけ統合失調症は急性期及び慢性期について)を担当する。
- 精神科救急を経験する。
- 精神科デイケアに参加する。地域精神医療の現場において、患者とコミュニケーションをとり、場合によってはデイケア・プログラムを自ら担当して、統合失調症を中心とした精神疾患の理解と、治療的アプローチの実際を経験する。
- 1年目に担当した症例のうち、精神科対応が必要だったものを提示し、診断及び治療等について学習する。
- 適宜、必要に応じて行われる「臨床レクチャー」を受講する(以下リスト参照)。
指導医の講義を受講したり、自ら講義を行うことも経験する。
精神科臨床レクチャーのリスト:
- 精神医療の歴史
- 精神症候学・精神科診断
- 精神科医療に関する法律及び社会資源
- 精神科薬物療法
- ECT
- 精神療法(総論、支持的精神療法、精神分析的精神療法、認知療法など)
- 器質性精神障害・症状精神病
- せん妄・薬剤性精神障害(ステロイド、INF等)
- アルコール依存症及び薬物依存症
- 痴呆及び老年期精神障害
- てんかん/EEG
- 統合失調症
- 気分障害
- 身体表現性障害(心気症)
- 不安性障害・強迫性障害
- 睡眠障害
- チーム医療と集団力動
- リエゾン・コンサルテーション
- ターミナルケア・緩和ケア
- 精神科リハビリテーション及びケースマネージメント
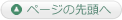
 目次に戻る
目次に戻る
