Home > 医学生・研修医向け情報 > 後期研修案内 > 腎臓内科

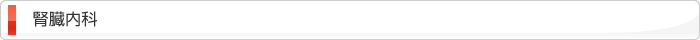
1. 中央病院腎臓内科の紹介:その位置と特色について
京都市の西北側(JR山陰線円町駅から徒歩5分)に位置する本院の腎臓内科は、市内を横断する丸太町通りを中心としたエリアのおおよそ西半分をその診療圏としています。
腎疾患の急性期から腎不全期までを総合的に診療できる病院は本院しかないため、京都民医連内の病院・診療所はもちろんのこと、地域の開業医からの紹介や京大病院や府立医大病院からの紹介も積極的に受け入れています。
本院では、腎臓内科は腎疾患診療だけではなく、血液透析を中心とした血液浄化療法全般を担い、ICUに準ずる病棟での急性血液浄化療法も担当しています。また、人数は少ないが腹膜透析(CAPDが主)も行っています。
また、糖尿病が透析導入の原因疾患の第一となっている現状に立って、糖尿病診療にも関与しています。腎臓が反応の中心臓器となる膠原病や血管炎などの疾患にも従事しており、多発性骨髄腫や悪性リンパ腫などの血液疾患の治療も担当している若手腎臓内科医もいます。
本院病理科は電子顕微鏡を有しており、光顕標本から蛍光抗体、電顕標本まですべての標本作製を院内で実施し、組織診断までを一貫して行い、腎生検診断は腎臓内科医が担当しています。毎月1回、腎生検カンファレンスを腎臓内科医、病理医、臨床検査技師の参加で開催しています。
なお、当院の透析診療は前身の右京病院時代の1970年から始めています。開設当初から府立医大で始められた腎移植治療に積極的に関わり、移植患者の紹介ばかりでなく、移植後透析再導入例も受け入れています。
2.腎臓内科研修の目標
- ふたつの専門医資格を取得する。すなわち、日本腎臓学会の腎臓専門医と日本透析医学会の透析専門医の資格である。どちらも認定内科医取得後3年の臨床経験と研修が必要。
- 腎臓病あるいは腎合併症の診断、治療の基本的診療能力を身に付ける。
- RPGNや急性腎不全などの急性期治療や腎障害を合併した重症期治療の経験を積む。
- 外来で腎炎・ネフローゼや腎不全管理を行える。
- 透析導入を計画的に行い、慢性透析に円滑に移行できるようにチーム医療を進めることができる。
- 医療福祉制度にも一定の知識を持ち、患者指導ができる。患者組織(本院には透析前腎臓病患者組織として「あじさい会」、透析患者組織として「さつき会」がある)にも積極的に関与する。
- このために必要な診療技術の習得を行う。尿沈査所見、腎臓の画像診断(特に腹部エコーについては実際に施行できる)、腎生検技術、腎生検組織の診断、ブラッドアクセスの作製(手術は助手を務める)と管理技術(穿刺は十分な技術を身に付ける。シャント造影やPTAを経験する)、CAPD症例の経験、カテーテル挿入手術に関わる、外シャントの使用経験。
3.当科の陣容と実績および京都民医連第二中病院と川端診療所の陣容
- 腎臓内科医(透析診療にも従事) 5名 (この外 常勤泌尿器科専門医1名)
- 腎臓外来(3名で担当) 週5単位(夜診1単位)
- 透析室(別館2階) 透析台数40台。患者数130名前後。夜間透析も週日施行。
- 透析室看護師 21名 臨床工学技師 9名
- ICU透析 透析台数3台。
- 血液浄化治療の内容:HD、HDF、CHDF、PE(DFPP)、PMX、LDLアフェーレシス、GCAP、LCAP
- 年間透析導入数:04年32人 05年25人 06年18人 07年19人 08年20人
- 年間腎生検数:04年18件 05年7件 06年20件 07年25件 08年22件
京都民医連では、腎透析医療は中央病院のほかに、京都の東に位置する京都民医連第二中央病院と鴨川沿いにある川端診療所の二つの施設でも行われている。
〈第二中央病院〉
透析台数 10台
腎臓外来 週1.5単位(小西憲子医師、武下清隆医師)
〈川端診療所〉
透析台数 35台
腎臓外来 0.5単位(小西憲子医師)
オンラインHDFも実施している。
指導医の専門分野と専門医資格
- 腎透析科科長 木下千春(島根医大1996年卒)
日本透析医学会認定専門医、日本内科学会認定内科医・日本腎臓学会認定専門医
糖尿病分野にも力を入れている。
- 総合内科科長 神田千秋(京大医学部1973年卒)
日本腎臓学会認定専門医・指導医、日本透析医学会認定専門医、日本内科学会認定内科専門医
腎病理、特に電顕診断専門。腎透析全般を担当。初期臨床研修の指導にも従事。
- 集中治療科科長 井上賀元(滋賀医大2001年卒)
日本救急医学会認定ICLSコース認定ディレクター・インストラクター、協議会認定ICD、日本腎臓学会認定専門医、日本内科学会認定内科医。
血液疾患と救急医療にも力を入れている。初期臨床研修の指導にも従事。
- 医員 神田陽子(信州大医学部2000年卒)
日本腎臓学会、日本透析医学会、日本内科学会所属
- 〈第二中央病院〉
武下清隆(府立医大1986年卒)
武田英希(京大医学部2004年卒)日本内科学会認定内科医
-
〈川端診療所〉
所長 田中義浩(関西医大1994年卒)
日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業医
-
〈非常勤〉
小西憲子(京大医学部1966年卒)
日本腎臓学会認定専門医・指導医・症例評価委員、透析医学会認定専門医・指導医、日本内科学会認定内科医
4.研修プログラム
〈1年目〉
- 入院症例を担当することによって、腎疾患診療の基本を学習する。20例以上。
- 腎炎、ネフローゼの基本的な治療を習得する。
- 指導医の元に透析を1単位受け持ち、外来透析管理の基本を学ぶ。
- 穿刺技術については1年でおおむね習得する。
- ダブルルーメンカテーテルの挿入技術も習得する。
- いくつかの腎透析関連の手術や検査に立会い、基本的事項について学習する。
- 症例報告を1題は行う。
〈2年目〉
- 重症例や緊急透析導入を受け持ち、主治医として基本的な対応ができるようになる。
- 腎生検については助手ができるようになる。
- 指導医の下に外来を1単位担当する。主に受け持ち入院症例を中心に行う。
- 透析単位を指導医なしで受け持つ。管理医師は別にある。
- シャント手術に助手として入る。10例以上。
- 症例報告を日本腎臓学会西部部会あるいは透析医学会に1題は行う。
- 患者教育を講師として行う。
〈3年目〉
- 1年目を指導しながら透析単位を受け持ち、主治医としての役割を担う。
- 腎臓外来を1単位受け持つ。初診患者や紹介患者の初診対応を行う。
- 腎生検については術者として生検を行う。
- 希望者はシャント手術の術者の経験を積む。
- シャントPTAについても術者あるいは助手として経験する。
- 患者教育およびスタッフ教育を講師として行う。
〈カンファレンスなど〉
- 毎週水曜日に急性血液浄化カンファレンスを行っている。
- 隔週木曜日午後に腎抄読会を行っている。
- 毎月第3木曜日夜に腎生検カンファレンスを行っている。
5.本院における腎臓内科専門研修の特徴あるいは特色は何か。
学会の研修プログラムをきちんと踏まえて行うことは勿論として、いちばん強調しておきたいことは、受身の研修ではなく、少しでも日々の診療内容が向上するように、新しい診療技術の導入とその育成を一緒に力を合わせて作っていく能動的な研修でありたいということです。私たちは現状の水準に満足はしていません。そのために診療技術の向上と新しい技術の導入に積極的に取り組んでいます。
たとえば、井上医師はシャントPTAの技術習得にチャレンジし、若手臨床工学技師と一緒に急性血液浄化法についての勉強会をしています。このように新しい診療内容を立ち上げるために一緒に取り組む経験こそがいちばんの研修となると信じています。
私たちの考える腎臓内科のイメージあるいはあり方を列挙してみましょう。
- 腎臓内科はチーム医療の実践である。
- 腎臓内科は健診段階から人工臓器治療・移植医療(本院では移植治療は行っていないが)まで幅広い領域をカバーしている。
- 腎臓内科はあらゆる科の重症期、終末期合併症としての腎不全診療に関わっている。
- 透析医療に従事することにより、副甲状腺機能亢進症のような内分泌疾患、透析骨症などの骨合併症や整形外科疾患への対応、多発する循環器合併症や感染症、透析アミロイド症などの代謝変性疾患、ACDKに合併する腎癌に見られる悪性腫瘍の合併、掻痒症などの皮膚疾患などなど、実に多彩な合併症への対応能力が求められる。総合内科的な力量ばかりでなく、内科以外の科に関わる合併症にも対応する知識と経験が必要という特色がある。
- 腎臓内科医はコーディネーター上手が大事。
6.それぞれの腎臓内科医からの一言
〈神田千秋医師〉
「一芸に通じれば百芸に通じる」―これは宮本武蔵の「五輪書」に書かれている言葉である。一方、「専門バカ」という批判的立場がある。臨床医はこの両者の微妙なバランスの上にあると思う。16歳で発症したMPGNの患者さんを30年近く診た。今は自宅近くの透析施設で元気に通われており、患者会の催し物などでお会いすることがある。患者さんと一緒に歳を重ねながら、腎臓病とじっくりと付き合っていく、それこそが腎臓内科医の生きがいというものではないだろうか。
〈木下千春医師〉
私が研修医になる以前に、腎臓は全身の影響を受けやすい、だから腎臓内科医は、全身の病気に一定精通している必要があり、まずは、内科医としての足腰をしっかり鍛えてほしいと、ある先生に言われたことがあります。患者さんを前にしたとき、プライマリーな力が必要となるのは確かだと実感します。中央病院での研修においては、症例的に典型的な腎炎から時には稀な疾患まで経験ができます。また、入院から外来管理まで1人の患者さんを継続してみていく事が大きな力になると思います。透析導入も比較的多く、導入期から維持透析の管理まで一貫して行っていくこも大切です。
私自身まだまだ、勉強したいことがたくさんあります。一緒にがんばってみませんか。
〈井上賀元医師〉
腎臓内科医は、尿所見異常から腎生検・慢性腎不全・透析導入と、腎臓の一生を見ることができます。ただ、同時に、患者さんの一生ともじっくりと付き合っていかなければいけない覚悟が必要です。当院の腎臓内科では全身をみるトレーニングを徹底的に行います。
私自身、今後急性血液浄化にも力をいれ、救急・集中治療の分野で難治性とされてきた病態を少しでも改善の方向に向けることができればと思っています。
ともに、腎臓という窓から人を診てみませんか?
