Home > 医学生・研修医向け情報 > 初期研修案内 > 研修プログラム > 2012年度 臨床研修プログラム > 選択必修科研修(2.小児科研修)

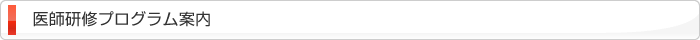
2012年度 臨床研修プログラム
2011.4.28 京都民医連中央病院臨床研修部
Ⅱ. 選択必修科研修 2. 小児科研修
研修期間は2ヶ月とする。
【獲得目標】
小児疾患は多くの面で内科と異なった特性をもっている。将来小児科を専攻しない医師にとっても、小児を診察できる力量を身につける必要がある。そういった背景をふまえ、2-3年目の研修医が、小児医療における知識・技能・態度を習得することを目標とする。研修期間は2か月間とする。
【行動目標】
- 正常児の発育・発達を理解し、評価ができる。
- 日常よくみる小児の疾患ならば、1人で対応できる。
- 小児の救急疾患に関して、初期判断と対応ができる。
- 代表的な慢性疾患の病態と管理について理解している。
- 重症度の評価ができ、適切に指導医または専門医にコンサルトできる。
- 母子保健の意義を理解し、予防接種等が指導医の元で実施できる。
- 患者家族の心情を理解し、良好なコミュニケーションがとれる。
1. 経験すべき症例
【行動目標】
プライマリケア医として経験すべき症例について別記している。入院、外来、救急医療の中で担当医として経験することが望ましい。
【研修方略】
毎月の研修委員会と修了時の研修総括会議で、症例の経験を確認する。
2. 集中講義
【行動目標】
研修期間中に経験が不足しがちな内容について、集中講義を行う。
【研修方略】
下記内容について、指導医とともに週1回程度学習会を行っていく。
- 感染性疾患についての外来対応について
- 慢性疾患管理について(喘息、てんかん、尿所見異常)
- 予防接種の知識について
- 検査の見方
- 小児保健の知識
3. 病棟研修
【行動目標】
- 入院患者を担当することで、患児および家族の身体的、心理的、社会的側面についても全人的に理解できる。
- 患者・家族対応の上で責任ある態度がとれ、良好な信頼関係ができる。
- 基本的な身体診察が、系統的かつ正確にできる。
- 診断・治療・在宅療養・社会資源の活用において適切な対応ができる。
- POSに基づくカルテ記載ができ、週間サマリー・退院総括・諸文書が適切に書ける。
- 患者様の療養の上で、他職種とともに患者様を中心としたチーム医療が行える。
【研修方略】
- 研修期間2ヶ月間の小児科入院症例について、すべて担当医として受け持つ。
- 研修期間中は、指導医・常勤医が必ず主治医として対応し、指導責任者を一人固定するが、研修医の指導は集団的に行う。
- 小児科病棟回診には必ず参加し、入院担当患児についてオリエンテーションを行う。その際に、患児の身体的、心理的、社会的側面からの問題点を適切にあげ、他職種とともに問題の解決を行うようにする。
- POSに基づきカルテを記載し、必要な場合にはサマリーを書けるようになること。
【評価】
研修終了時に、自己総括を行い、指導医・病棟婦長からチェックを受ける。
4. 外来研修
【行動目標】
- 外来診療の流れが理解できる。
- 主訴や症状に応じた診察と処方ができる。
- 初診患者の問診、診察を行い、適切な診断治療計画が立てられる。
- 慢性疾患患者の長期的な医学管理の仕方を学ぶ。
- 患者の医療費負担に配慮した、適切な診療ができる。
【研修方略】
- 研修開始時には、入院受け持ち患児についての外来担当医として担当する。
- 研修開始後に小児科外来を週2回程度見学する。
- 研修終了までに外来単位を週2回程度補助的に担当する。
【評価】
研修終了時に、自己総括を行い、指導医・主任看護師からチェックを受ける。
※ 外来研修として、週2単位程度の小児科単独診療所での外来研修(地域医療研修)を選択することができる。
5. 検査および技術研修
【行動目標】
- 別掲した検査・手技について適応・合併症を理解し、結果判読ができる。
- プライマリーケアに必要な、診断・治療・救命手技を獲得する。
【研修方略】
(1)一般手技
研修期間中は、病棟・入院での全ての一般手技を指導医と共に経験する。
(2)診察手技
- 医療面接: 外来見学時には、看護師とともに問診をとる。
- 乳幼児の診察: 成人とは異なる診察法を研修し、異常所見をきっちりと見れるようになる。
- 耳鏡検査: 急性中耳炎の鼓膜所見が判別できるようになる。
(3)検査
腹部エコー:検査適応を判別し、腸重積の所見を指摘できるようになる。
【評価】
- 別に定めるチェックリストに基づき到達度を、自己および指導医により評価する。
- 毎月の研修委員会で到達度を評価し、個々の達成を追及する。
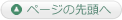
 目次に戻る
目次に戻る
