Home > 医学生・研修医向け情報 > 初期研修案内 > 研修プログラム > 2012年度 臨床研修プログラム > 必修科研修(3.地域医療研修)

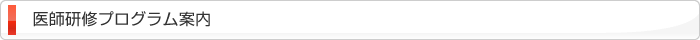
2012年度 臨床研修プログラム
2011.4.28 京都民医連中央病院臨床研修部
Ⅰ. 必修科研修 3. 地域医療研修
研修期間は必修科の場合は1ヶ月、選択研修期間に選択する場合は2ヶ月以上とする。
【一般目標(GIO)】
- プライマリケア、家庭医に必要な知識・技能・態度が何かを知る。
- 患者の問題を解決するための医療・介護・保健のネットワークの中での医師の役割を学ぶ。
- 地域の住民・患者組織とともに進める医療のあり方について実践を通して学ぶ。
- 医療・介護と経営のかかわり、医療・介護をよくする活動を学ぶ。
【行動目標(SBOs)】
- 診療所で必要とされる知識・技能・態度を習得する。
- 医療・保健・介護のネットワークの中で患者の問題解決を行う。
- 地域の住民、患者とともに進める医療活動を学ぶ。
- 診療所を取り巻く各種施設の役割を体験する。
【方略(strategy)】
- 診療所長の外来・訪問診療を見学する。
- 診療所の管理会議に参加し、経営や医療活動の状況を知る。
- 訪問看護ステーションやヘルパーステーションなどを含んだ患者のカンファレンスに出席する。
- ケアマネージャーのケアプラン作成をともに行う。
- 訪問看護ステーションの看護師とともに在宅患者の訪問を行う。
- 患者会に出席し、患者の意見を聞く。
- 医療懇談会などのとりくみに参加する。
【評価(evaluation)】
- 逐次、スタッフや指導医から評価を受ける(評価内容は指導医に集中する)。
- 毎月、初期研修委員会を他職種の参加も得て開催し、到達度を評価する。
- 研修修了時に自己総括を作成する。それに基づき、指導医および医局で到達度と課題について評価を受ける。
選択期間中に、2ヶ月以上地域医療研修を選択する場合は、上記に加え以下のプログラムを研修する。
1)病棟研修
1.内科研修の1)病棟研修と同じ。
2)外来診療研修
【一般目標(GIO)】
外来担当医として、患者さんの症状や訴えに配慮し、患者さんを全人的に理解し良好な関係を保ちながら、診断・治療・生活指導に適切なマネージメントができる。
【行動目標(SBOs)】
- 自己紹介をし、適切な医療面接ができる。
- 主訴や症状に配慮した診察ができる。
- わかりやすく平易な言葉で説明できる。
- 各々の診察のステップや外来の流れが説明できる。
- 必要な生活習慣の情報を聞き取り、適切な生活指導ができる。
- 患者の医療負担に配慮した診察ができる。
- 新患患者の臨床症状から鑑別疾患を列挙し、適切な診断・治療計画を立てられる。
- 慢性疾患患者を対象として、長期的な医学管理ができる。
- 適切な処方ができる。
- 他職種と適切な連携がとれる。
- 適切なコンサルテーションと紹介ができる。
- 外来治療か入院治療かもしくは在宅治療かの判断ができる。
【研修方略(Strategy)】
- 導入として、指導医や常勤医の外来見学を複数回行う。
- その後、オリエンテーションとして、初診患者1~2例を指導医の立ち会いのもとで診察し、援助・指導を受ける。
- オリエンテーション後は週2単位程度の外来を担当する。
- 外来診療中適宜または外来終了後、指導医もしくは外来指導担当の常勤医とともに診療内容を検討し、指導・点検を受ける。
【評価(Evaluation)】
- 可能な範囲で、外来看護婦、受付事務、薬局、検査技師、放射線技師から、外来終了後検討会の場で指摘をうける。
- 毎月、初期研修委員会を他職種の参加も得て開催し、到達度を評価する。
3)在宅医療研修
【一般目標(GIO)】
入院・外来医療との違いを理解し、良質の在宅医療・在宅ケアを実践し、提供することができる。
【行動目標(SBOs)】
- 在宅医療における家族・介護者の重要性を認識する。
- 在宅高齢者・障害者を一個の人格として尊重し、敬うことができる。
- 患者とその家族のあり方・価値観の多様性を認識する。
- 在宅医療と在宅ケアにおける各職場の役割とチーム医療の意義について認識する。
- 在宅医療・在宅ケアの適応について理解する。
- 在宅患者の以下の機能的側面での評価ができる。…日常生活動作能力、運動機能、痴呆、包括的アセスメント
- 家庭環境の評価ができる。
- 家族介護の評価ができる。
- 在宅ターミナルを行うことができる。
- 在宅医療においてとりうる各々の治療手段についてその利点と欠点・限界を認識する。
- 在宅医療に関わる診療報酬の概要と介護保険制度の概要について認識している。
- 在宅医療における栄養管理評価および諸種の栄養管理法が施行できる。
- 患者、家族及び介護者、訪問スタッフと効果的に意志疎通をはかることができ、カンファレンスを開催できる。
- 主な在宅向け医療・福祉・保健サービスを処方することができる。
【研修方略(Strategy)】
- 週1単位程度の往診を行う。
- 往診指導医を決め、往診後のカルテカンファレンスを行う。
- 研修開始前に受持患者を指導医とともに往診し、オリエンテーションを受ける。
- 適宜他職種とともにカンファレンスを行う。指導医におけるバックアップ往診を適宜行う。
【評価(Evaluation)】
- 毎月、初期研修委員会を他職種の参加も得て開催し、到達度を評価する。
- 適宜、自己評価・指導医評価・在宅チームメンバーからの評価を集中しフィードバックを施行する。
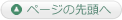
 目次に戻る
目次に戻る
