Home > 医学生・研修医向け情報 > 初期研修案内 > 研修プログラム > 2012年度 臨床研修プログラム > 必修科研修(2.救急部門研修)

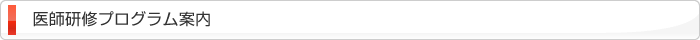
2012年度 臨床研修プログラム
2011.4.28 京都民医連中央病院臨床研修部
Ⅰ. 必修科研修 2. 救急部門研修(麻酔科を含む)
研修期間は3ヶ月とする。
【一般目標(GIO)】
緊急を要する疾患・病態に対する初期評価および初期対応ができる。
【行動目標(SBOs)】
- 別掲のリストに示す疾病・病態について初期評価および初期対応ができる。
- 必要な事項を適切にカルテおよび日誌等に記入ができる。
- 必要な事項を適切に主治医もしくは次の救急対応医に申し送りができる。
- 当直・当番医のその他の役割(他院所よりの依頼、入院患者の事故、行方不明への対応、災害時の対応など)について理解し、おおむね全うできる。
- 救急時間外対応における院所の約束事を理解し、尊重して診療にあたれる。
- 症状の推移に対する注意や時間内再診などの指導ができる。
- 救急時間外対応においても、礼節を保持できる。
- 救急時間外対応においても、患者の身体的・心理的・社会的側面での変化について把握・分析・総合できる。
- 救急時間外対応においても、患者の基本的人権と医師の義務について理解する。
【研修方略(Strategy】
- 研修開始前に、救急疾患に関する講義および院内のオリエンテーションを受ける。
- EMコールなどの救急対応場面に最大限自覚的に参加する。
- 病棟当番や救急外来などを経験する(当初指導医または常勤医とともに行い、到達度によって、ファースト・コール、バックアップ付きの一人立ち、事後のカルテチェックへと段階的に経験する)。
- 当直を経験する(当初2ヶ月は副直とし、到達度に応じてファーストコールに移行)。
- 対応した患者に関して、カルテチェック、フォローアップを行う。
【評価(Evaluation】
- 逐次、スタッフや指導医から評価を受ける(評価内容は指導医に集中する)。
- 毎月、初期研修委員会を他職種の参加も得て開催し、研修プログラムの到達度を評価し、必要な改善や変更を加える。
- 研修修了時には、チェックリストに基づき、自己総括を作成する。それに基づき、指導医および医局で到達度と課題について評価を受ける。
- 救急部門研修中に希望があれば、京都府立医科大学附属病院にて麻酔科での研修を1ヶ月間行うことができる。その期間のプログラムは以下のとおり。
【到達目標】
- 日常の一般的手術の麻酔管理について、各種麻酔法、麻酔薬、麻酔器についての基本的知識を習得する。
- 麻酔対象患者の問題点・麻酔管理方法の選択に関して検討し、一般的な麻酔前評価ができ、かつ簡潔・的確な症例提示ができる。
- 指導医の指導の下に一般的な麻酔管理と付随する周術期管理ができる。
【基本方針】
- 麻酔前評価および麻酔、周術期に発生が予測される問題の解決のための必要な情報収集・情報整理能力を習得する。
- 手術室における手術患者の麻酔にアシスタント、麻酔担当医として参加し、全身麻酔、脊髄麻酔に必要な知識、技術、検査法を習得する。
【研修内容】
- 手術室と麻酔科外来の運営システムを理解する。
- 他科医師・看護師・ME技師、放射線技師などすべてのスタッフの役割を認識し、チームの一員として協調して診療にあたる姿勢を養う。
- 基本的なモニタリングについて理解する。
- 指導医の指導のもとに、麻酔対象患者の術前回診、術前評価を行い、必要な追加検査などについて主治医にオーダーする。
- 指導医とのペアにて麻酔対象患者の最適な麻酔法の選択を行い実施する。
- 麻酔科におけるより専門的な手技・技術とは,以下のようなものである。
- 末梢静脈路確保
- マスクによる人工呼吸
- 気管内挿管
- 機械的人工呼吸器操作
- 経鼻胃管の挿入
- 動脈圧ライン留置
- 中心静脈カテーテル留置
- 消毒法
【教育体制】
- 毎朝症例検討会を行い、当日のすべての麻酔症例について症例提示し、指導医を中心に全員で検討する。
- 毎夕症例検討会を行い当日のすべての麻酔経過についての検討を行う。
- 毎週末の症例検討会にて,担当麻酔患者の術前評価、麻酔法、経過についての報告を行い,全員で討議する。他の症例についても討論に参加し検討を行う。
- 月末の地域別症例検討会に参加し、問題症例についての検討に参加し、必要があれば自ら問題症例についての報告の方法について指導する。
- 麻酔シミュレーターを用いることにより、さらに多くの麻酔知識の実践能力を養うことができる。
- 毎月の学外招聘講師による講演会に参加し,最新の基礎的、臨床的情報と接する。
- 指導医とともに当直し,緊急手術の麻酔や病棟での救急蘇生などの実践について指導する。
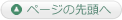
 目次に戻る
目次に戻る
