Home > 医学生・研修医向け情報 > 初期研修案内 > 研修プログラム > 2012年度 臨床研修プログラム > 必修科研修(1.内科研修)

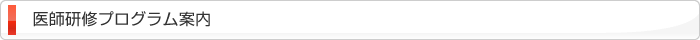
2012年度 臨床研修プログラム
2011.4.28 京都民医連中央病院臨床研修部
Ⅰ. 必修科研修 1. 内科研修
1. 病棟研修
【一般目標(GIO)】
担当医として入院患者を受け持ち、患者さんを全人的に理解し、良好な信頼関係を保ちながら、指導医・上級医と相談して入院から退院までの診断・治療・療養に関して最適の総合的かつ個別的なマネージメントができる。
【行動目標(SBOs)】
- 別掲のリストに示す疾病・病態について、病棟受け持ち対応ができる。
- 別掲のリストに示す基本的手技・身体診察ができる。
- 別掲のリストに示す検査の指示及び判断ができる。
- 患者さんの身体的、心理的、社会的(労働や生活の状況も含めた)側面について把握・分析・総合できる。
- 入院医療に関わる他職種の役割と責任を理解し、カンファレンス等を通してチーム医療ができる。
- 患者・家族と良好な信頼関係を保ち、必要な説明や指導ができる。
- POSに基づくカルテ記載及び退院に関わる指示、調整、サマリー記入ができる。
- 重症者、臨死者のケアおよび看取りができる。
- 入院に関わる諸文書(入院診療計画書、退院療養計画、入院証明、返書、かかりつけ医意見書など)の作成ができる。
- カンファレンス、回診などの際に適切なケースプレゼンテーションができる。
- 必要に応じて、他の医師や専門医への依頼、相談、対診ができる。
【研修方略(Strategy)】
- オリエンテーション期間を設け、業務手順の説明や他職種の業務の見学・体験など主治医業務に必要なオリエンテーションを受ける。
- 適宜指導医及びスタッフ医師の指導を受ける。
- 「回診」を通じて、必要な指導を受ける。
- 「カンファレンス」を通じて、必要な指導を受ける。
- 他職種とのカンファレンスを定期的に持つ。
- 退院した患者のサマリーを内科学会の「病歴要約作成の手引き」に準じて記入する。作成した退院時要約は、指導医の確認を受ける。
- 退院前後訪問を行い、退院後の患者さんの生活状況を知る。
【評価(Evaluation)】
- 毎月、初期研修委員会を他職種の参加も得て開催し、研修の到達度を評価し、必要な改善や変更を加える。
- 各科研修の終了時にチェックリストに基づき、自己総括を作成する。それに基づき、医局および初期研修委員会で到達度と課題について評価を受ける。
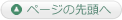
2. 病棟外研修
希望に応じて、3ヶ月程度の期間、週に半日程度の診療所での地域医療研修(在宅診療研修や外来医療研修)を行うことができる。内容は、3.地域医療研修の1)外来医療研修、2)在宅診療研修に沿った研修を行う。
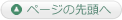
3. コミュニケーション研修
【一般目標(GIO)】
社会人として、また医師として、一般常識、マナーを身につけ、患者・家族、スタッフと良好なコミュニケーションが持てる。
【行動目標(SBOs)】
- 社会人としての一般常識、マナーを再確認し、良好な信頼関係を確立する。
- 診療に必要な情報を患者、家族から得ることができる。
- 病状、治療、予後などについて、患者、家族に説明し、理解と同意を得ることができる。
- チーム医療の構成員として、求められる医師の役割、責務を自覚し、行動できる。
【研修方略(Strategy)】
- 接遇の講義を受ける。
- 模擬患者(SP)演習において指導を受ける。
- 担当患者、家族との話し合いを当初は指導医監督下、後には独力でおこなう。
- カンファレンスの主催を、当初は指導医監督下、後には独力でおこなう。
【評価(Evaluation)】
- 逐次スタッフ、指導医から評価を受ける。
- 初期研修委員会において多職種からの評価をおこない必要な、改善、変更を加える。
- OSCEにて評価を受ける。
- 担当患者、家族からの評価を得る。
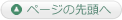
4. 医療安全・医療倫理研修
【一般目標(GIO)】
- 医療の安全性確保を行動決定の重要な判断基準として認識し、行動できる。
- 一般的な医療行為および特別な治療や診断の介入に際して、医療倫理的側面を認識し、それに関して個人あるいはチームで対応できる。
【行動目標(SBOs)】
- 主要な診療行為における事故と合併症の発生のメカニズムについて理解する。
- 事故合併症発生の際の行動マニュアルに沿って対応できる。
- ミス・ニアミス・合併症の発生に際して、報告書(アクシデント・インシデントレポート)を提出し、再発防止のための行動変容をはかれる。
- 患者それぞれに固有の価値観、生き方、選択があることを認め、患者に情報を伝え、自発的な同意(インフォームド・コンセント)を得ることができる。
- 医療者が勧める治療を患者が拒否した場合や、患者が効果のないあるいは有害な治療を要求したときに適切な対応ができる。
- 患者の判断能力を評価し、患者の判断能力が欠けているときに、適切な対応ができる。
- 終末期の患者の以下のような状況に適切に対応できる。
- 栄養や輸液を含む生命維持の治療を控える、あるいは中止する場合。
- 悪い知らせを伝え、患者・家族の意見を聞く。
- 蘇生禁止(DNR=Do not resuscitate)の指示を書く。
- 患者が自殺幇助や安楽死を医師に要求した場合。
- 患者との間に維持されている守秘義務を変更したい旨を伝える。
- 情報開示と医療過誤の現場において、真実を伝える原則に基づいて伝えることができる。
【研修方略(Strategy)】
- 文献学習と講義を受ける。
- 指導医、スタッフ医を含んだカンファレンスで倫理的問題について検討する。
- 指導医あるいはスタッフ医とともに患者・家族と面接し、対応について実地に学ぶ。
【評価(Evaluation)】
- 逐次、スタッフや指導医からフィードバックを受ける。
- 毎月、初期研修委員会を他職種の参加も得て開催し、到達度を評価する。
- 研修修了時に総括を作成し、指導医および医局で到達度と課題について評価を受ける。
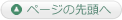
 目次に戻る
目次に戻る
